はじめに
発達障害という言葉が社会に浸透してきた現在でも、実際に身近な家族に発達障害をもつ人がいる場合、どう関わり、どう支えていけばよいのか悩む人は少なくありません。家族は、当事者にとって最も身近で、長期的に関係を築いていく存在です。そのため、適切な理解とサポートが極めて重要です。
本稿では、発達障害の基礎的な知識に触れながら、親や兄弟といった家族がどのように当事者を支えられるのか、また、家族自身が健やかに関わり続けるためのヒントを探っていきます。
発達障害とは何か?
発達障害とは、生まれつき脳の機能の発達に偏りがあり、社会生活において特有の困難を示す状態を指します。主に以下の3つが代表的です。
-
自閉スペクトラム症(ASD)
-
注意欠如・多動症(ADHD)
-
学習障害(LD)
発達障害は「障害」という言葉が使われていますが、これは「能力の偏り」であり、苦手な部分と同時に得意な部分も持ち合わせていることが多いのが特徴です。この「特性」を正しく理解し、活かすことがサポートの第一歩です。
家族が直面する課題
発達障害の診断を受けると、親や兄弟など家族もさまざまな課題に直面します。
1. 情報の不足と混乱
最初にぶつかるのが「何が起きているのか分からない」という戸惑いです。診断名が示されても、それが具体的にどういう意味を持つのか、どう関わればいいのかが分からず、混乱することがあります。
2. 社会的な偏見
「しつけの問題では?」「甘やかしすぎたのでは?」といった偏見にさらされることも、家族にとって大きなストレスとなります。こうした周囲の無理解が、家族の孤立を深めてしまうこともあります。
3. 兄弟姉妹への影響
発達障害のある子どもにかかりきりになってしまい、健常な兄弟姉妹が我慢を強いられるケースもあります。また、兄弟自身も悩みや不満を抱えてしまうことがあります。
4. 将来への不安
「この子は自立できるのだろうか」「自分がいなくなった後はどうなるのか」といった将来への不安も、親にとっては大きな心配の種です。
家族ができるサポートとは?
発達障害を持つ家族を支えるためには、「理解」「受容」「工夫」「連携」が鍵となります。それぞれについて詳しく見ていきましょう。
1. 特性を理解する
まず重要なのは、当事者の特性を正しく理解することです。例えば、自閉スペクトラム症の子は、コミュニケーションが苦手でもルーティンに強い、細部に気づくなどの特性があります。ADHDの子は、集中が続きにくい反面、好きなことには強い集中力を発揮する場合もあります。
親は診断名だけでなく、実際にどういう状況で困りごとが出て、何に対しては強みを持っているのかを観察することが大切です。
2. ありのままを受け入れる
「普通にしてほしい」「他の子のようにできればいいのに」と願う気持ちは自然なことですが、その思いが強すぎると、子どもは自己肯定感を持てなくなってしまいます。「この子はこの子のペースで成長している」と信じ、特性も含めて受け入れる姿勢が、本人の心の安定につながります。
3. 環境を整える
本人の特性に応じて、家庭内での環境やルールを調整することも効果的です。例えば、視覚的なスケジュール表を使ったり、音や光への過敏さに配慮した空間を作ったりすることで、本人が落ち着いて過ごせるようになります。
また、「○○しなさい」ではなく「○○したら××できるよ」といった行動の見通しを立てやすい伝え方に変えるだけでも、トラブルを減らすことができます。
4. 兄弟姉妹とのバランス
兄弟姉妹に対しても、発達障害の特性を分かりやすく説明することが必要です。「わがまま」ではなく「脳の特性なんだ」と理解してもらうことで、怒りや嫉妬の感情が和らぐことがあります。
また、兄弟姉妹の気持ちを丁寧に聞く時間を設けたり、「あなただけとの時間」を意識して作るなど、バランスの取れた関係性を保つ努力も重要です。
5. 専門機関との連携
ひとりで抱え込まず、教育・福祉の専門家と連携することが、家族にとって大きな支えとなります。発達障害支援センター、療育機関、学校の特別支援コーディネーターなど、専門的な知識と経験を持つ人たちの力を借りることは、決して恥ずかしいことではありません。
親・家族自身のケアも大切
支える側の心と体が疲れていては、継続的なサポートは難しくなります。親自身のセルフケアもとても重要です。
-
支援団体やピアグループでの情報交換
-
家族以外の信頼できる人に話す
-
可能であれば、一時的に支援を利用してリフレッシュする
自分の感情に気づき、時には休むことも「サポート」の一部です。
発達障害とともに生きる「家族の力」
発達障害を持つ本人にとって、家族の存在はかけがえのないものです。家庭が安心できる場であることが、社会生活を送る上での「土台」となります。
また、家族自身も発達障害のある人とともに過ごす中で、多様性への理解が深まり、人との違いを受け入れる力を養うことができます。「普通」ではなく「その人らしさ」を尊重する視点を家族が持つことで、社会全体もまた少しずつ変わっていくでしょう。
おわりに
発達障害のある人を支えることは、時に困難や悩みを伴うものです。しかし、「できないこと」に目を向けるのではなく、「できること」「伸ばせる力」に目を向けることで、本人も家族も、前向きに日々を積み重ねていくことができます。
大切なのは、完全を目指すことではなく、「一歩ずつ共に歩むこと」。発達障害を持つ家族と向き合う中で、家族それぞれが柔軟さと優しさ、そして力強さを育んでいくことができるのです。
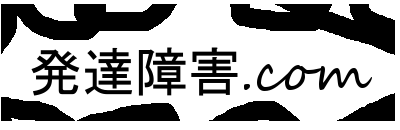
LEAVE A REPLY